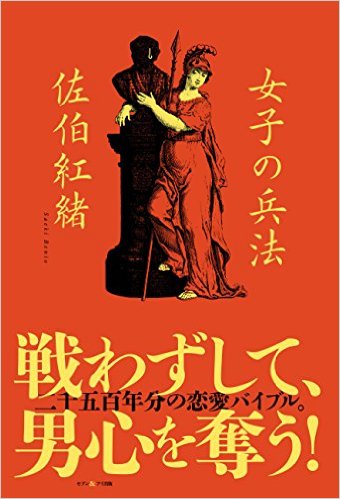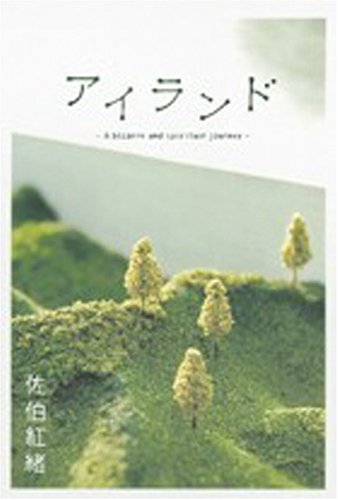映画『沈黙ーSilenceー』感想
マーティン・スコセッシ監督映画『沈黙-Silence-』のプレミア上映に行ってきた。
遠藤周作の小説『沈黙』の映画化である。
(以下、若干ネタバレ含みます)
舞台は江戸初期の隠れキリシタン弾圧下の長崎。主人公は先に来日して棄教したという師フェレイラの消息を探しにやってきたロドリゴという宣教師だ。
テーマはひたすら暗く重く、ひとことで言ってしまうと「こんなにひどいことがあるのに、なぜ神様は黙っているのか」という話である。
個人的にウルウルきてしまった部分からまずいわせてもらうと、まず冒頭からいきなりの「ヒグラシの声」。これを聴いた瞬間、しょっぱなから涙が止まらなかった。
なぜなら、その一瞬で、監督が西洋人なのに「セミの声」を音楽として聴ける耳を持っていることがわかったからである。
これはすごいことなのだ。どうしてかというと、セミの声を「音楽」として右脳で聴けるのは世界中で日本人だけだからだ。海外ではあの虫をバグと呼び、左脳で「雑音」として認識する。だから、海外に時代劇を輸出する時はセミの声をわざわざ消すくらいだ。
それなのに、スコセッシ監督はこの音をあえて残し、しかも「音楽」として効果的に使用した。だからこれを最初に見た時、ものすごい「私たちのことをわかってもらえてる感」があったのだ。
そして、ああこの映画を観に来てよかった、と心から思えたのである。
ささいなことかもしれないが、こういった細部へのこだわりは作品全体に通底する。セミの声を「よきもの」として理解してくれている監督は、きっと「私たち」の心にも寄り添ってくれるだろう、そう思えたのだ。
当時の長崎の再現も、ぜんぜん違和感がなかった。撮影は台湾で行われたというが、観ているうちにちゃんと時空を超え、当時の長崎へ飛ぶことができた。
もちろん、史実どおりにいくならポルトガル人宣教師同士の会話は英語でなくポルトガル語であるべきだし(映画『アポカリプト』ではメル・ギブソンが本当に古代マヤ文明の言語を使っていた)、日本人通詞が英語を使うようになったのはおそらく幕末からなので、井上以下、皆さんあんなに英語が達者なワケがない。
しかし、それにすら違和感を覚えさせなかったのは、ひとえに巨匠の手腕のおかげだろう。そこはもう本当に不思議なのだけど、観ている間にそのことに気づかないくらいそのウソは自然につかれていた。おかげでベルナルド・べルトルッチ監督映画『ラスト・エンペラー』で年老いた西太后が紫禁城でいきなり幼い溥儀に英語で話しかけた時のような残念な気持ちは少しも味わわずに済んだのである。
日本を描くハリウッド映画にありがちな「不気味の谷」現象もなかった。メインに最高レベルの日本人俳優、しかも下手をすると当時あの時代にいたことがあるんじゃないか、と思えるような風貌の人たちがキャスティングされていたせいだろう。
要であるキチジロー役の窪塚洋介を始め、井上役のイッセー尾形、通詞役の浅野忠信他、ほんとうにみんなよかった。芝居のすごさもさることながら、フィット感が半端なかった。主演のアンドリュー・ガーフィールド演じるロドリゴの相棒ガルペ役がSW7でカイロ・レンを演じたアダム・ドライバーというのも面白かった。(この人は道をつきつめすぎてひん曲がってしまう役がホントウによく似合う)
そして言うまでもないことだが、劇中もっとも現代の我々の感覚に近いのはキチジローである。踏み絵は踏む、何度も裏切る、なのに信仰が捨てられない。囚われのロドリゴにキチジローが泣きながら言う、「平和な時代なら自分は善人でいられた、なのにこのようなつらい時代に、勇気も何もない自分のような弱い人間に居場所はあるのか?」と。
狐狸庵先生(面白エッセイを書く時の遠藤周作の通称)が作中もっとも身を入れて描いたのはこのキチジローであることは明白である。
この映画は実を言うと、「キリスト教と日本的なものが人を通じてぶつかり合う話」ではない、と思う。
なぜなら、劇中で井上や通詞の口を借りて何べんも繰り返されるのは「我々はあなた方の教えにはとても敬意を払っている。我々のものとは共通するところもたくさんある。しかし、あなた方がその教えを通じて我々にしようとしていることはまったく気に入らない」というセリフだからだ。
井上は悪人ではない。当時の国際情勢を知り抜く政治家としてはしごくまっとうな選択をしているだけだ。拷問も楽しんでしているわけではなく、必要だからやっているのだ。布教を許した他の国々がどうなったかをみればその答えは明らかである。
ちなみにこれは私の個人的な考えだけれど、こういう「西洋的なもの」と「日本的なもの」の最大の壁はひとことでいうと、「サヨナラ」と「アーメン」の違いなんじゃないかと思っている。
「サヨナラ」とは「左様なら」、つまり「そうですか、なら仕方ありませんね」という意味だ。
それに比べ「アーメン」というのは「そうでありますように」という意味である。
どちらも死者を送り出すときにも使われる言葉だが、このふたつの違いはそれこそ致命的なくらい大きい。「そうか、ならしょうがないね」という、古来日本人特有のあきらめの死生観と、「そうであってほしい」となお何かを願わずにはいられない西洋人のライフイズビューティフル感覚には、それこそ天と地ほどの大きな違いがあるからだ。
遠藤周作とスコセッシ監督の面白い共通点は、この違いを認識しつつ、互いに深い部分ではわかりあっているところである。遠藤周作が日本人でありつつ終生敬虔なカトリック信者であり続けたように、スコセッシ監督もまた、西洋人でありながら「古来からの日本的なもの」をこよなく愛し続けている。だからそれが今の日本から失われつつあることをおそらくとても悲しんでいる。我々日本人の大半よりも悲しんでくれている。だからこそ、あそこまで丁寧に美しく描いてくれた。その象徴が冒頭のセミの声である。そのことを感じて私は泣いたのだ。
もうここまでいくとユングの世界で、この「違いをなんとかしてわかり合おうとする」テーマを扱った小説にもうひとつ、ローレンス・ヴァン・デル・ポストの小説『影の獄にて』がある。大島渚監督映画『戦場のメリークリスマス』の原作となった小説だ。
この小説には映画でビートたけしが演じたハラというすごくおもしろい軍曹が出てくる。これがまさに「外国人には絶対理解できない、古来日本的ななにか」が服を着て歩いているような男で、このハラが日本軍の捕虜となったローレンスをめちゃくちゃにいじめ抜く。だから他の捕虜たちはハラが大嫌いなのであるが、ローレンスだけは「違う、あの目の輝きを見ろ、あれはいじめでも憎しみでもなく、神話を生きているすごい男なんだ」とその本質を見抜くのである。
だからハラのほうもそんなローレンスをなんとなく好きになって、二人の間には不思議な友情が芽生える。ハラはいじめながらも機嫌のよいときにはローレンスを呼びつけて酒の相手をさせたり、ローレンスが殺されるところをクリスマスだからと助けたりするのだが、そこにはやはり立場や考え方の違いなんかがあり、「なんでおまえは捕虜なのにいさぎよく自決しないんだ、そうしたら俺はおまえをもっと好きになれるのに」「いや違う、つらくてもなお生きるのが本当に大事なことなんだ」といった平行線の問答が繰り返される。
そして戦争が終わって立場が逆転し、ハラが処刑される最後の晩にローレンスが駆けつける。そして、そこで交わされた最後の会話で両者はようやく着地点にたどり着く。しかしその時は既に遅く、ハラは直後に処刑されてしまう。
そして、この物語の結びになるのは「人間というのは、ほんとうに大事なところではいつも手遅れになるのではないだろうか」という言葉である。
12歳の時に初めて観た日本映画、溝口健二監督『雨月物語』を美しいと感じる感受性を持っていたスコセッシ監督は、きっと『沈黙』の劇中でフェレイラが嘆く「この国にはキリスト教は絶対に根付かない、なぜなら、この国の人間は自然以外なにも信じないからだ」という言葉の意味もよくわかってくれているのだろう。そしておそらく、『影の獄にて』でハラとローレンスの間に芽生えた友情のなんたるかも理解しているに違いない。だから、映画の冒頭とラストでは日本的なものに敬意を表し、我々に自然の音だけをひたすら聴かせてくれたのだ。
だから映画『沈黙』は、互いの置かれた文化的背景に心からの敬意を示し、有史以降だれも答えを出せていない「神様はこんな世界でなぜ沈黙しているのか」という、あまりにも遠大な問いになんらかの答えを見出そうとした二人の巨匠の凄まじい共同作業ではないかと思う。
それが、正確なメッセージなのかどうかまではわからないけど。